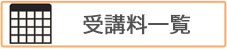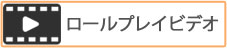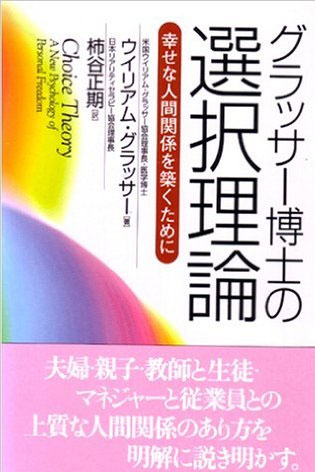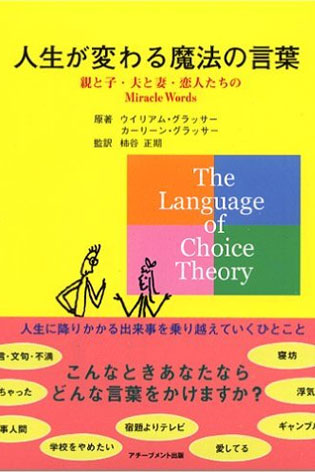クオリテイ・スクールの取り組み
Creating Quality Schools: The New Trend in Education
柿谷正期(Masaki Kakitani)
The movement to create Quality Schools is gaining momentum. So stated Dr. William Glasser in a speech in Boston presented in 1999. The pursuit of quality was originally emphasized by W. Edwards Deming, the father of the Quality Management movement. What Deming was trying to do is explained by the teaching of Choice Theory, which was formulated by Glasser. He was been inspired to adopt Deming's idea of quality into education. Quality School training has proven to be effective and practical in its use. This article is an attempt to introduce key Quality School concepts.
はじめに
教育改革にはさまざまな試みがなされてきているが、クオリティ(上質)に焦点をあてた教育改革はこれまでなかった。グラッサー(Glasser)の提唱するクオリティ・スクールは、上質に焦点を合わせた取り組みである。米国では全校あげての取り組みをはじめた学校は、200校を越えている。フロリダ州のレイクギブソン中学校の校長をしていたケッセル博士 (Kessell)は、日本での講演のときに、いろいろな試みをしてきたけれども、これしかないと思うようになったのがクオリティ・スクールであった、と述べている(Kessell、1997) 3年間の取り組みで、規律違反の問題の減少、欠席数の減少など顕著な変化が起こっている。学校が基本的欲求充足の場となるときに、問題は予防される。
グラッサー博士
グラッサーは1925年生まれでロスアンゼルスに在住している精神科医である。1965年に著した『現実療法』で知られ、以来公教育に大きな関心を持ち、教育に関する著作も多く著している。ニューヨークのジョンソン市は、グラッサーの『落伍者なき学校』(1969)をベースにした取り組みでめざましい教育改革をした。その取り組みから、アル・ママリー(Albert Mamary)は教師のためのコンピューター・プログラムを開発し、グラッサー(1999)はこれを推奨している。『クオリティ・スクール』(1990) は、同じ路線の教育改革であるが、デミングが企業で上質に焦点を合わせて成功したように、教育で上質に焦点を合わせることで成功するとの呼びかけであった。デミングとの接点は、グラッサーの選択理論(1984)を知ったデミングやその仲間たちが、自分たちが取り組んできたことは、実は選択理論そのものだったとグラッサーに伝えてきたときに始まる。
システムの問題
デミングは、組織に問題があれば、システムに80パーセントの問題があり、人の問題は20パーセントとしていたが、晩年には、98パーセントはシステム、 2パーセントが人の問題であると言った。仮にデミングに日本の教育の問題点は何かと尋ねると、同じ答えが返ってくるであろう。教育のシステムに98パーセント問題があると。他人が評価するシステム、強制されるシステム、競争のシステム等々、システム変革への取り組みが求められる。デミングのマネジメントに関する14項目(柿谷正期、1996)は、不思議なことにデミング賞の存在する日本でもあまり知られていない。デミングが自分の考えは日本でゆがめられたと言っているのも、このあたりに問題があるのであろう。
上質(クオリティ)とは
デミングは、上質は定義できないが、見れば分かると言った。グラッサーは上質とは上質世界(クオリティ・ワールド)に入っているものと定義している。上質世界とは、グラッサーによると、頭のなかにある小さな場所で、その人の基本的欲求を満たす人、物、信条などが入っている場所である。母親は乳児を愛し、世話をする。乳児は母の庇護、愛を受けて愛と所属の欲求が満たされる。これが繰り返されるなかで、母親のイメージ写真が乳児の上質世界に、写真アルバムのように貼られることになる。上質世界に入っているものは、その人にとっては重要なものであり、人を動機づけるものとなる。デミングの話、書物等を調べて、グラッサーは、上質の条件と特徴を次のようににまとめている。上質とは、
- 温かい人間関係の中で生まれる。
- 強制のないところから生まれる。
- 自己評価から生まれる。
- そのとき最善のもの。
- いつでも改善できるもの。
- 役立つもの。
- 気分の良いもの(しかし、破壊的でないもの)。
温かい人間関係
グラッサーは現在の公教育の問題点は何かと聞かれ、温かい人間関係が教師と生徒との間に欠如していることと答えている。教師と生徒が敵対関係にあっては、上質は達成されない。敵対関係になるのは、外的コントロール心理学を使うからであるとグラッサーは指摘する。通常、刺激-反応理論として知られている外的コントロール心理学は、人を他人がコントロールできると考える。そのために適切な方法は何かを考え、飴と笞の手法も取り入れる。「学校教育の失敗と成功に関する新しい考察」と題した論文で、グラッサー(1997)は、「学校で失敗するのも結婚で失敗するのも原因は同じです。ほとんどの人が刺激-反応という外的コントロール心理学を実践しているからです。」と述べている。温かい人間関係のある状態をコネクテッド(connected)、そうでない状態をディスコネクテッド(disconnected)と表現し、子供にとって親または教師と温かい人間関係を持つことの重要性を強調している。これに関しては、「若者を害から護る」と題した長期間に渡る研究結果が医学誌(JAMA、1997)に発表されている。この論文では、親もしくは教師と温かい人間関係が持てない若者は、暴力、薬物依存、愛のないセックス、そして精神病の4つの害をもろに受けやすくなると述べられている。
温かい人間関係を築くために、グラッサーは次の7つの大罪を犯さないよう戒めている。
- 批判する。
- 責める。
- 文句を言う。
- ガミガミ言う。
- 脅す。
- 罰する。
- ほうびで釣る。
教育現場では、批判は教師の義務であり責任であると確信している傾向がある。批判をしないでどうするのだ、との疑問が起こりそうである。批判をしないためには、自己評価が重要となる。例えば、自己評価の重要性を知っている教師は、教育実習生に対して批判をしないで、3つの質問をすることもできる (Simon、1978)。
- あなたのしたことでよかったことは何ですか?
- もう一度同じ機会が与えられたら、どこをどのように変えますか?
- 私にお手伝いして欲しいことが何かありますか?
この3つの質問は自己評価を促す質問である。批判は一切ない。教師はフィードバックをする立場にあるが、批判をしないでフィードバックをする技術を磨く必要がある。
米国初のクオリティ・スクール
米国で自他ともにクオリティ・スクールであると最初に認められた学校は、ミシガン州のハンティントン・ウッズ校である。ハンティントン・ウッズ校は当初 370名が在籍する公立の小学校として開校された。現在は400名が在籍していると聞いている。幼稚園から5年生までが在籍している。370名の生徒のうち保護者が220人ボランティアとして学校に係わっている。毎週150時間~200時間がボランティアによって提供されている時間である。これは職員 4~5人分に相当する。1クラス25人の生徒に教師と助手が係わるのであるが、2クラスを一緒にして、ティーム・ティーチングをしている。50人の生徒に対して教師2人、助手2人、そして保護者のボランティアが係わっている。50人の生徒は同学年ではなく、3学年が一緒のクラスで、必ずしも全員が同じことに取り組んでいるわけではない。テーブルは丸形で、各自動き回りながら自由に勉強できる仕組みである。ハンティントン・ウッズ校のテスト結果は、ミシガン州の平均に比べて抜きんでている。国語のテストで州平均が49.5点に対して、ハンティントン・ウッズ校は83.2点。算数は州平均が60.5点に対してハンティントン・ウッズ校は85.3点である。
クオリティ・スクールの理念
ハンティントン・ウッズ校は次のような理念を掲げている。クオリティ・スクールに共通した要素である。
- 人は5つの基本的欲求を持っている。学校は、生徒、教師、保護者にとって、欲求充足の場である。
- 競争ではなく、協調することで最高の学習ができる。
- 強制のあるボスマネジメントではなく、リードマネジメントの環境で生徒は成功する。
- 脅したり、罰したりしないで、問題は話し合って解決する。
- 自己評価が上質(クオリティ)を達成する鍵である。
(1) 基本的欲求
グラッサーは人間には基本的欲求があり、集約すると5つとなるとし、それらを次のように表現している。
- 愛・所属の欲求
- 力の欲求
- 自由の欲求
- 楽しみの欲求
- 生存の欲求
生存の欲求は、身体的なもので、水を飲み食物を摂取し、空気を吸うことによって満たされる。人間の頭脳の脳幹と呼ぶ部分が無意識のうちに調整して、私達に必要な行動を促している。後の4つは心理的欲求である。愛・所属の欲求は、愛し愛される、仲間の一員でありたい、友人と係わりたいという欲求である。これは、4つの心理的欲求の中でももっとも重要であると言えよう。力の欲求は自分の価値を感じたい、重要であると感じたい、人のお役に経ちたいという欲求である。自由の欲求は、自分で選んで、自分で行動したいという欲求である。楽しみの欲求は、楽しい思いをしたい、新しいことを学んでみたいと思う欲求である。本来勉強は楽しいものであるはずなのに、楽しみに直結していないことに問題がある。ハンティントン・ウッズ校は、基本的欲求を満たすことに焦点を合わせているので、当然楽しい学校作りにとりくんでいる。その結果学校が楽しく、生徒たちは「夏休み要らない。学校に行く方が楽しい」ということになり、長期夏休みのないユニークなスケジュールで運営されている。愛・所属の欲求を満たすために、教師は校長をはじめ全員が朝生徒たちを校門のところで出迎え、アメリカらしいハギング(抱擁の挨拶)で1日が始まる。
(2) 共同学習
競争ではなく、協調で最高の学習が得られるという理念は、共同学習(Cooperative Learning)の形で実践されている。グループ学習と呼ばずに共同学習と呼ぶ理由は、共同学習の方がお互いに生徒同士が共に学習する姿勢を感じるからである。共同学習では生徒が生徒に教える、教えられるということが普通となる。教えることは学習することであり、教えられないということは、理解の度合いを高める必要を示唆しているかもしれない。また教えることによってコミュニケーションの技術を磨くことにもなる。教えることで生徒は、力の欲求を満たすことができ、教えられる生徒も理解が進むことで勉強が楽しくなり、同時に達成感(力の欲求)を得ることになる。競争の問題点については、コーン(1986) がその著書の中で、データーを駆使しながら指摘している。(柿谷正期、1997) 共同学習についての研究は、米国ではめざましい。
(3) リードマネジメント
ボスマネジメントに対して、強制のない選択理論に基づいたマネジメントの仕方をリードマネジメントと呼ぶ。ボスマネジメントは、外的コントロール心理学に基づくマネジメントであり、強制がその大きな特徴の一つである。強制されると自由の欲求が満たされない。クローフォード(Crawford, 1993)たちは、ボスマネジメントとリードマネジメントを対比させて次のように言っている。
- ボスマネジャーは生徒を動機づけることに心を配り、リードマネジャーは、動機づけの障害を取り除く。
- ボスマネジャーは誰が悪かったかを探し、リードマネジャーは何が悪かったかを探す。
- ボスマネジャーは欠陥の責任を取らせ、リードマネジャーは欠陥を防ぐ方法を調べる。
- ボスマネジャーは生産性に全員の注目を向けさせ、リードマネジャーは「上質」に全員の注目を向けさせる。
- ボスマネジャーは個人の達成を協調し、それに報奨を与え、リードマネジャーはグループの達成を強調し、その達成を認める。
- ボスマネジャーは「勉強しなさい」と指示を与え、リードマネジャーは「勉強をしやすくなる」方法を確立する。
これらは、学校にも職場にもあてはまるものである。少しの違いがやがては大きな違いを作ることになる。ボスとリーダーの違いを次のように述べることもできる(グラッサー、1990)。
- ボスは駆り立て、リーダーは導く。
- ボスは権威に依存し、リーダーは協力を頼みとする。
- ボスは「私」と言い、リーダーは「私たち」と言う。
- ボスは恐れを引き出し、リーダーは確信を育む。
- ボスはどうするかを知っているが、リーダーはどうするかを示す。
- ボスは恨みをつくりだし、リーダーは情熱を生み出す。
- ボスは責め、リーダーは誤りを正す。
- ボスは仕事を単調なものにし、リーダーは仕事を興味深くする。
(4) 罰しない
問題行動に対して仮に「当然の結果」という表現を使っても、多くの場合「罰」になってしまうことが多い。クオリティ・スクールに罰はない。問題が起こったら話し合って解決する。子供たちに、問題を起こした人に対してどうしたら良いかと尋ねると、多くの子供たちは「罰を与える」と答える。それほど「罰」は私たちの社会に浸透している。しかし、「罰」に抑止効果がどれほどあるかは、刑務所の満杯状態を見れば、疑問が出てくる。子供の上質世界に教師が入っていれば、その教師の言葉を子供は無視できない。教師の教えている教科にも無関心ではおられない。クオリティ・スクールの教師はリアリティセラピーを使ったカウンセリング手法を身につけているので、子供の願望を聞き出しながら、「それを続けていて、君の得たいものが得られると思う?」と自己評価を促すことをする。教師と生徒との間に温かい人間関係が存在していれば、話し合いで解決しない問題はあまりない。
(5) 自己評価
グラッサーはデミングの教えていること、書いていることを調べるなかで、デミングの言葉で実に重要な言葉があることに気づいた。それは、「人は他人を評価してはならない」という言葉である。自己評価という言葉は、日本で誤用されており、使う人によって意味が異なっているが、正しくは「他人によって評価される他者評価に対して、自分の学習、行動、性格、意欲などを自分自身で評価すること。」(恩田彰、1999)。間違った用法は、自己像、セルフイメージ、自己肯定感の高低と捕えることである。自己評価はself-evaluationであって、self-esteemではない。グラッサーは現実療法の中の重要なステップとして、はじめから自己評価の概念を持っていた。そうであるが故に、人々が聞き逃してきたデミングのこの言葉に注目したのであろう。グラッサーはデミングの言葉を少し言い換えて「人は他人を公に評価してはならない」と言っている。頭の中でなされる評価は、私達が上質を知っているなら、それと異なるものに触れたときに、おのずからなされる。しかし大切なのは、当事者が自己評価をすることである。クオリティ・スクールの理念の一つとして挙げられるものとして、この自己評価は欠かせないものである。産業界でも上質なものは、上から命令されてできるものではなく、また検査過程を厳しくして達成されるのではなく、当事者の自己評価によってのみ可能である。教育の世界では、教師が生徒を評価するシステムが厳然として存在している。これを自己評価するシステムにシフトすることが必要となる。
クオリティ・スクールの6つの基準
クオリティ・スクールであることを宣言するためには、最低次の6つの基準を満たしている必要がある(ウイリアム・グラッサー協会、1999)。
- 時折の出来事は別として、規律違反の問題とは無縁である。
- 州の習熟度試験や大学進学のために必要なSATのような試験で、生徒が高得点を取っている。そしてこのようなテストの重要性が強調されている。
- その教科を履修したという能力の証明がないものには評価点をつけない。すなわち、Bやそれ以下の評価点をつけない。完全な習熟が強調される。小学校、中学校、高校では、生徒は教師もしくは教師の定めた人に対して、自分が習熟したことを実際に見せることができなければならない。習熟していなものについては、評価点はつけない。評価点として残るものはすべてAだけである。『選択理論』で説明されているように、無意味な強制学習(スクーリング)は排除され、役立つ教育のみが行なわれている。
- 毎年、すべての生徒が「上質」と思われる何かに取り組んでいる。これは習熟しているというレベルをはるかに越えたものである。そのような取り組みはすべて、AもしくはA+の評価を受けるものである。これは、熱心に取り組む生徒が、もっと出来ることを示す機会ともなる。
- 生徒も教師も私生活と学校生活で選択理論を実践している。保護者は『選択理論』の読書会に参加するよう勧められ、選択理論を理解している。
- 教師、生徒、保護者、管理職が、デミングの考えに従って、学校は喜びに満ちていると言える。
以上の6つの基準に対して、各学校が自己評価をして、クオリティ・スクールと呼ばれるのにふさわしいレベルに達していると思えたら、クオリティ・スクールであることを宣言する。ハンティントン・ウッズ校に続いて、いくつかの中学校、高校がそのレベルに達しており、学校関係者の注目を集めている。
教育の定義
グラッサーは、実生活で役立たないものを学校で学習させていることが多々あると指摘し、そのようなものは真の教育ではなく、強制学習(スクーリング)であると区別している。歴代大統領の名前を最初から現在まで間違いなく、暗記することを要求することは、このスクーリングに入るものと言えよう。多くの暗記ものはこの範疇に入る。真の教育(エデュケーション)は、知識の取得ではなく、知識を使うことであると主張している。現在の教育システムでは、Bの成績をとる生徒とAの成績をとる生徒の違いは大差ない。試験の5分前に忘れるか、試験の5分後に忘れるかの違いであると言われる。
まとめ
日本ではまだ、全校あげてクオリティ・スクールの取り組みをしている学校はまだない。比較的良い取り組みをしている学校があるとすれば、選択理論に近いことが実践されているようだ。デミングのマネジメントに関する意見は重要なものではあるが、デミング自身が選択理論のような理論をもたなかったので、日本でデミングの考えはゆがめられ、その結果普遍化しなかったとも考えられる。日本の学校でクオリティ・スクールの取り組みをしようとしても、困難があるのは、学校自体に裁量権があまりないからである。校長がクオリティ・スクールの取り組みをしようとしても、教師の採用権もあるわけではなし、外的コントロール心理学を信奉する教師がいる限り、学校全体の取り組みは困難となる。筆者がアメリカの校長たちと話して思うことは、アメリカの校長は若いということと、かなりの裁量権が与えられているということである。停年まじかの校長に学校改革を期待することは不可能ではないとしても、無理に近い。可能にする方法は、教師の研修を学校主体で取り組み、自分たちの学校はどのようになったら良いと思うのか話し合いながら、選択理論をしっかり学ぶ取り組みをすることであろう。この話し合いには当然、上質とは何か、共同学習とは何か、自己評価のアイディアをどこまで徹底できるか、学校に存在している強制にはどんなものがあるか、学校で教師や生徒が満たされていない欲求は何か、学校で無益な学習(スクーリング)が要求されているだろうか、習得した知識は使われているだろうか、将来使われる可能性はどのくらいあるだろうか、学校が喜びに満たされている環境になるためにはどのようなことが必要なのかという問いかけが含まれる。こうしたことを長期に渡る、一貫した研修(柿谷正期、1996)で話し合っていく過程で、選択理論の原則が私生活にも学校にも浸透していくことを期待したい。グラッサーのクオリティ・スクールは机上の空論ではなく、喜びに満ちたクオリティ・スクールがいくつも誕生しつつある。日本でそのような取り組みが早くなされることを期待したい。
- Crawford.D.K., Bodine,R.J. & Hoglund R.G. (1993), The School for Quality Learning. Illinois: Research Press.
- Deming, Edwards(1994). The New Economics. Boston: MIT Center for Advanced Educational Services. NTTデータ通信品質管理研究会訳(1996) 『新経営システム論』NTT出版
- Gabor, Andrea(1990) The Man Who Discovered Quality. New York: Random House.鈴木主税訳(1994) 『デミングで甦ったアメリカ企業』草思社
- Glasser, William (1965) Reality Therapy. New York: HarperCollins.真行寺功訳(1975)『現実療法』サイマル出版会
- (1969) Schools without Failure. New York: HarperCollins.佐野雅子訳 (1977)『落伍者なき学校』
- (1986) Choice Theory in the Classroom. New York:HarperCollins.
- (1990) Quality School. New York: HarperCollins. 柿谷正期訳(1994)『クオリティ・スクール』サイマル出版会
- (1993) The Quality School Teacher. New York: HarperCollins.
- (1997) "A New Look at School Failure and School Success" PHI DELTA KAPPAN (April, 1997) 柿谷正期・寿美江訳(1997)「学校教育の失敗と成功に関する新しい考察」『現実療法研究』第4巻・第1号(1997年8月)
- (1998) Choice Theory. New York: Harper Collins. 柿谷正期訳(2000)『選択理論』アチーブメント出版、星雲社
- (1999) Creating the Competence Based Classroom. The William Glasser Institute
- JAMA(1997) "Protecting Adolescents From Harm"(September 10, 1997, Vol. 278 No. 10)
- 柿谷正期(1994)「クオリティ・スクール」『現実療法研究』第2巻第1号
- 柿谷正期(1996)「クオリティ・スクール(2)」『現実療法研究』第3巻第1号
- 柿谷正期(1997)「競争より共生」『現実療法研究』第4巻第1号
- 柿谷正期(1999)「報奨による罰」『現実療法研究』第5巻第1号
- Kessell, Gwen(1997)「クオリティ・スクールへの道程」(講演テープ)日本リアリティセラピー協会
- Kohn, Alfie(1993). Punished by Rewards. New York: Houghton Mifflin Company.
- (1986). No Contest: The Case Against Competition. New York: Houghton Mifflin Company.
- Mentley, Kaye & Ludwig, Sally. Quality Is the Key Michigan: KWM Educational Service, 1997
- 恩田彰、伊藤隆二編(1999)『臨床心理学辞典』「自己評価」(杉村健)
- Simon, Sidney B.(1978) Negative Criticism Publisher unknown.
- Sullo, Robert A. (1997) Inspiring Quality in Your School. NEA Professional Library.
- (1999) The Inspiring Teacher. NEA Professional Library.
- The William Glasser Institute (1999). Programs, Policies & Procedures Manual.
NPO法人 日本リアリティセラピー協会理事長、米国ウイリアム・グラッサー協会認定シニア・インストラクター、臨床心理士
本論文は「グローバル市場競争時代における教育・人材育成のあり方」研究委員会報告書(財団法人 地球産業文化研究所、2000年5月)に掲載されたものです。財団法人 地球産業文化研究所