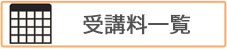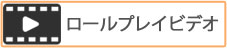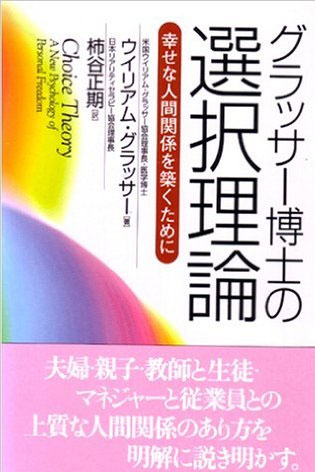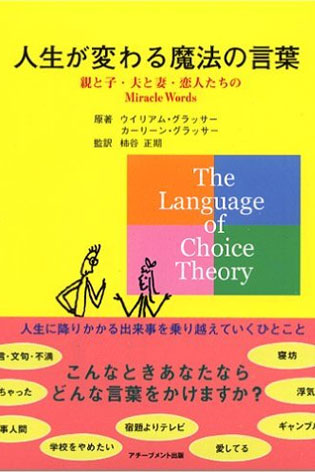選択理論書籍推薦の言葉
グラッサー博士の『選択理論』をお薦めします
国分康孝/こくぶ・やすたか (カウンセリング・サイコロジスト, Ph.D.)
結論から言えばグラッサーの『選択理論』(アチーブメント出版)の一読をすすめたい、というのがこの拙文の骨子である。その理由は四つある。
- カウンセリングと心理療法の識別を主張している私は、「臨床心理士だけがカウンセラーか」と事あるごとにカウンセリング界の人々に檄をとばしている。それゆえにグラッサーの選択理論のように人間関係の問題の予防を提唱する理論には、カウンセリング関係者は是非なじんで頂きたい。
- エリスの論理療法に影響を受けた私にとっては、思考も行動も感情も自分が選んだものである。したがって「~によって不幸にさせられた」のではなく、「自分で不幸な道を選んだのだ」という選択理論は、論理療法にとっては、援軍来るとういことになる。ところで選択理論(Choice Theory)とは私の言い換えでは「自分の人生の主人公は自分である」というオートノミー・セオリー(Autonomy Theory)とでも言うべきもののように思われる。
- グラッサーもロジャーズもエリスと同じように理論構成を次々と変えて今日に至っている。今回の「選択理論」がグラッサーの考えの集大成かもしれないが、今後また発展するかもしれない。この柔軟性にふれるためにも本書を読んでほしい。
- ところで本書は柿谷正期さんの訳である。内容を噛んで含めるように日本語で表現している。翻訳の仕事に関心のある方はこの訳文のリズムとことばの使い方をモデルにするとよい。直訳と意訳を上手に統合したモデルである。(2000年6月28日)
村瀬 旻/むらせ・あきら (慶應義塾大学理工学部教授)
私がこの本で興味を持ったのは、世の中に流布している2つの問題に、グラッサー博士が革新的な見方を示し挑戦していることである。その一つは(1)外的コントロール心理学の信条についてであり、もう一つは(2)伝統的な心理療法/カウンセリングの進め方についてである。
- 『選択理論』では、「私たちがコントロールできる行動は唯一自分の行動だけである」、「すべての全行動(選択理論では、行為、思考、感情、生理反応を分離できないものとして、全行動と呼ぶ-これはとても優れた捉え方である)は、選択されたものである」と主張する。人は内的コントロールのもとで生きるとし、自律的人間像を打ち立てるのである。外的コントロール心理学では、環境によって人間の行動は変えられるとし、自律的人間像は廃される。本書の13章は「Redefining Your Personal Freedom(自由への道)」として、選択理論の原理にもとづく「個人の自由」が定義されている。興味あるのは、外的コントロール心理学の旗頭であるスキナーも『Beyond Freedom and Dignity(邦訳:自由への挑戦)』を著わしており、両者が共に「自由」について論じていることである。
- 選択理論にもとづくカウンセリングでは、過去に焦点を合わせない。クライエントが自分のために現在何ができるかを強調する。これは解決焦点化によるブリーフカウンセリングの進め方に近い。そしてこれは、最近、"これからの心理臨床のスタンダード"と称して出版された下山晴彦著『心理臨床の発想と実践』で範例として示されるような、クライエントの「人生の物語」を時間をかけて聴いていく伝統的な進め方とは全く異なるものである。
私の立場は統合主義であるので、内的か外的か、現在のみか過去をも含めるか、いずれの一方だけの見方をとらない。それらが補い合いバランスをとった見方が、人間にかかわる時には大切だと考えている。
『選択理論』を読んで最初に思い出したのが、仏典『ダンマパダ』の始まりの言葉である。「ものごとは心にもとづき、心を主とし、心によってつくり出される。(中村元訳)」 この言葉は紀元前に遡ることができる。歴史の中で人間についての概念には変遷がある。外的なコントロールに偏った見方からバランスを回復し、新しい世紀のカウンセリングをめざすために、私にとって『選択理論』は刺激的な書であった。
松原達哉/まつばら・たつや (立正大学教授)
文章が大変わかりやすく、過去でなく現在に焦点を合わせたカウンセリングで、私が開発した生活分析的カウンセリング「Life Analytic Counseling」とも共通する点があって、大変参考になり勉強になります。 あちこちにはっとするような名言「人は他人を評価してはならない」とか「子どものために親が出来る最高のことは、夫婦がお互いに愛し合うことである」など大変教えられることの多い本です。
最近のように人間関係のトラブルから殺人、自殺、けんか、離婚、依存症なども多い時代に、この本は21世紀の人生のバイブルではないかと思います。、、、、ゆっくり拝読して勉強したいと思っています。また、学生、院生、研修生などに大いにPRしたいと思っています。(2000年4月29日)